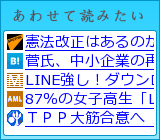モルガン銀行で資金為替部長、東京支店長などを歴任し、東京市場屈指のディーラーとして世界に名を轟かせ、「伝説のディーラー」と呼ばれた著者:藤巻 健史 氏が、今回の経済危機について展望するとともに投資家は今、何をするべきか等について提言している本を紹介します。
本書の「まえがき」で、自身を最も楽観的な意見を持っているマーケットパースンとした上で、以下のように述べています。
「サブプライム・ローン問題」とは、「金融資本主義の終わり」でも「悪魔が金儲け主義で劣悪商品を売りつけた結果」でも「デリバティブの問題」でも「米国経済の終わり」でありません。
金融商品の「ミスプライシング」から起きた技術的問題に過ぎないと思うのです。
(略)
このように「サブプライム・ローン問題」が単なる技術的な問題にすぎないのならば、その技術的問題を取り除きさえすれば、事態は急速に解決します。そうすれば、プラスの資産効果で、実体経済も急速に回復するはずです。だからこそ、私は、楽観的なのです。」
サブプライム・ローン問題は早晩終わり、次に来るのは資産インフレである。
そして、そのインフレが来て、現金が紙屑になる前に、今こそ株や土地などの資産に投資しておくべきと説いています。
<<ポイント>>
藤巻 健史 氏が説く、先読み投資術の本。
「100年に1度の危機」と騒がれている。サブプライム・ローン商品の価格の暴落に端を発した世界的な金融システム不安について、資本主義の崩壊だとまでいわれ、危機説が満ちあふれている。
これは、もともと高すぎたサブプライム・ローン商品が、値崩れにより「時価会計」の弊害が現れたもの。
金融機関では、理論価格より大幅に低い「バナナの叩き売り価格」で評価せざるを得なくなった。
その結果、巨額の評価損を計上せざるを得なくなった金融機関の見栄えが悪くなった。
さらに、デリバティブという「世になじみが薄い商品がらみ」だったので危機感があおられ、その恐怖感が事態を悪化させた。
サブプライム・ローン問題は早晩終わり、次に来るのはインフレである。
次の来るべき時代に備え、株や土地などの資産を持つべきだ。
と説いています。
本書:「100年に1度のチャンスを掴め!」です。
「サブプライム・ローン問題後のマーケットはこう動く」との副題が付いています。
本書は、著者:藤巻 健史 氏にて、2009年4月にPHP研究所 より、「PHPビジネス新書」の一冊として発行されています。
本書は、『Voice』に2008年9月から2009年1月にかけて掲載された「藤巻健史の国富論」をもとに大幅に加筆・修正されたものとのこと。
 至極正論と思います。
至極正論と思います。 いつの時代も流動性の悪化から
いつの時代も流動性の悪化から 一つの考え方として、至極ごもっともな考え方です。
一つの考え方として、至極ごもっともな考え方です。 現実は得てして地味なものです
現実は得てして地味なものです 非常に為になりました。
非常に為になりました。<<本書のエッセンスの一部>>
本書の帯ならびに表紙カバーの表裏には、以下のように書かれています。
汗水たらして貯めた資産を無駄にしないための先読み術!
来るべき次の時代に備えよ
危機の震源である米国の株価よりも日本株の下落が激しいのはなぜか?
来るべき次の時代に備える投資法
サブプライム・ローン問題に端を発し世界的危機により、実体経済が悪化し、さらに恐慌に至るのではないかといわれている。
資本主義の終わりとまでいわれている。
しかし果たしてそうだろうか。
「見えない怪物」が怖くてパニックに陥っているだけではないか。
事実、危機の震源である米国の株価よりも日本株のほうが大きく下落しているのだ。
今回の危機はどうなるのか?
投資家は今、何をするべきか?
「伝説のディーラー」が時代を見通し、提言する。
本書は、12章から構成されています。
全体が起承転結といった流れになっています。
ざっと章を追って概要を紹介します。
第1章では、「私は今、何をやっているのか?」
と題して、昨年の9月末までは、長期固定金利でお金を借りるだけ借りて、株(日本株と米国株が半々)と不動産と外貨建て商品を買っていたが、10月6日に日本株の全部と米国株の半分を売ったとの話題から始まります。
そして、10月下旬から「金融システム不安がさらに深刻化するリスクは低くなったと見て日米株を買い戻したとのこと。円は高すぎで、日本株は安すぎといった筆者のロジックを展開しています。
第2章では、「今回の危機の経緯」
と題して、サブプライム・ローンに関わる今回の経済危機に対する筆者の見方を論じています。
もともと高すぎたサブプライム・ローン商品が、「バナナの叩き売り」によって 理論値よりも安く取引され、その価格が時価となって各社の損益決算書の見栄えが悪くなり、株価が下落して資金調達に支障が生じ、流動性危機が生じたものとの見方です。
またこの流動性危機により信用収縮が起こり、逆資産効果などにより実態経済が悪化したものとしています。
第3章では、「事態を悪化させた恐怖心」
と題して、「日本株が他国の株式より大きく下がった理由は、「日本人の『右向け右、左向け左』の性格であるとともに「円高」のせいだと思われる」といった今回の危機では、マーケットをよく知らない人たちの無責任な発言が事態を悪化させたと言う面もあったのではないかとしています。
第4章では、「実体経済の悪化は恐慌に結びつかない」
と題して、実体経済の悪化の原因が「逆資産効果」であるという不況の原因がはっきりしているので処方箋を書くのは簡単と述べ、これが筆者が10月下旬から株式を買い始めた理由としています。
第5章では、「そろそろ峠を越したか?金融システム不安」
と題して、金融システム不安は今後深刻化しないと思ったことも10月下旬から株式を買い始めた理由としています。各国の政府・中央銀行の4つの政策(1.公的資金の投入、2..銀行間の賃貸の保証、3.不良債権の買い取り、4.時価会計の一時停止)が実行されれば、金融システム不安は峠を越すとの見方をその理由付けとともに述べています。
第6章では、「日本経済復活のシナリオ」
と題して、米国株の回復のステップと円安ドル高に基づく日本の景気回復のシナリオについて論じています。
第7章では、「政府が取るべき政策」
と題して、株価を上昇させる政策、マイナス金利論、円安誘導、欧米株への投資といった筆者の論を展開しています。
第8章、第9章では、「サブプライム・ローン問題解決後のマーケット(その1)(その2)」
と題して、本書の表題になっている「100年に一度のチャンス」について、「今後かなりの資産インフレが起こる」との筆者のこれからの時代の経済展望を論じた上で、汗水たらして貯めた現金や銀行預金が紙くず同然になっては、たまらないので、少しずつ株や不動産を買っておくのが賢明ではないかと説いています。
第10章では、「投資家は何をすべきか?」
と題して、中長期的に見て資産インフレは来ざるを得ないとの判断でインフレ時の資産運用、すなわち「借金をする」、「不動産を買う」、「株その他の金融商品を買う」という資産運用を一度にではなく「時間的分散投資」を考慮すべしと説いています。
第11章では、「デリバティブ取引の重要性」
と題して、「デリバティブについて、時に事件を引き起こすが、弊害ばかりをあげつらうべきではなく、いかに世界経済のために貢献してきたかを考えるべき」と正しいマーケット分析のためのデリバティブ理解のためのデリバティブ取引について、誤解、特徴、意義などを解説しています。
第12章では、「日本経済の課題諸々」
と題して、今日の日本では、パイの分配論が満ちあふれているが、パイ拡大論が必要ではといった問題を取り上げ、筆者の論を説いています。
<<本書で何が学べるか?>>
本書では、「伝説のディーラー」と言われた筆者の独自の観点からのサブプライムローンに端を発した世界不況の分析とこれからの経済展望と投資論が語られています。
基本的には、筆者も述べているように楽観論でマーケットパースンとしての願望も込めた天動説といった展開になっているように感じました。
データをもとに実証的に論じるというよりは、一流のマーケットパースンは、論理を超えた動物的嗅覚を持って先の時代を読み取るといった面もあるのかなとも感じました。
<<まとめ>>
これからの時代の資産運用といったことに関心がある人には、本書は、読んでおきたい一冊と思います。
なお本書の主要目次は、以下の内容です。
第1章 私は今、何をやっているのか?
第2章 今回の危機の経緯
第3章 事態を悪化させた恐怖心
第4章 実体経済の悪化は恐慌に結びつかない
第5章 そろそろ峠を越したか?金融システム不安
第6章 日本経済復活のシナリオ
第7章 政府が取るべき政策
第8章 サブプライム・ローン問題解決後のマーケット(その1)
第9章 サブプライム・ローン問題解決後のマーケット(その2)
第10章 投資家は何をすべきか?
第11章 デリバティブ取引の重要性
第12章 日本経済の課題諸々
(広告)
7月18日入場分以降の「マジカル・トワイライト&デイ・パス」も販売中!