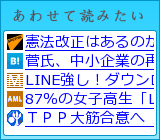生産現場の改善のための現場把握のポイントとなる「見える化」をターゲットにそのための具体的な方法とアイデアについて豊富な図解でわかりやすく解説している本を紹介します。
経営コンサルタントとして、特に教育・コンサルティング業界でTPS(トヨタ生産方式)ベースの人づくりに軸足をおいた実践活動で活躍中の筆者:石川 秀人氏は、「見る」ことについて以下のように述べています。
「視覚とは、可視光などの光情報をもとに外界の構造を推定する働きのことで、外界にある物体の色・形などについての情報、物体のカテゴリーについての情報、物体の位置関係のような外界の空間的な情報などを推定する感覚のことを指します。
(略)(視覚の「見る」について「大辞林」による12通りの意味を整理して)
など「見る」には様々な意味があり、「観る」(見物)、「看る」(世話)、「視る}(調査)とも書くことができます。
また英語でも、look(見る)、watch(注意して見る)、See(見る、調べる、わかる)、eye(じろじろ見る)、stare(見つける、にらむ)などの表現があります。
それでは、人間ではなく貴社ではどのような「見る」ことをお求めでしょうか。
またそれが見えることによって何をされたいのでしょうか。
本書では、製造現場における「見える化」について考えていきます。」
<<ポイント>
なかなか見えない製造現場の人の動き、不良の要因、業務プロセスといったことを「見える化」し、生産「現場力」を鍛えるカイゼンのアイデアを図解で分かり易く解説する本。
本書では、
見えないことの罪悪を対比して見える化の意義を確認することからはじまり、
- 『モノ』
- 『4M』
- 『QCDS』
- 『情報』
- 『日常管理』
- 『方向性および思い』
- 『全体および経営』
といった切り口から「見える化」のための手法を解説し、
生産「現場力」を鍛えるカイゼンのアイデアを説いています。
本書:「製造現場の見える化の基本と実践がよ~くわかる本」です。
「現場改善のための実践プログラム」との副題が付いています。
本書は、著者:石川 秀人 氏にて、2009年10月に秀和システムより「図解入門ビジネス」( How‐nual Business Guide Book)の一冊として発行されています。
<<本書のエッセンスの一部>>
本書の表紙カバーの下部には、以下のように書かれています。
生産「現場力」を鍛える
カイゼンのアイデア満載!
- 見えないことで何を失っているのか?
- 見える化の意義と効果がよくわかる!
- 創意あふれるモノづくりの現場とは?
- 見せる化のための仕掛けがわかる!
- チェックリストで「見える化度」を知る!
本書は、8章から構成されています。
本書の巻末に「特別編:見える化度が企業のレベルを表す」と題して、本書で述べている見える化に関して自社の見える化の度合いがどのくらいの位置づけにあるかを各項目の見える化について、0、1,2,3の3点満点で自己診断できる100項目からなるチェックリストが掲載されています。
本書の解説は、各項目、見開きの2ページ(3ページにわたるものもある)で緑・黒の二色刷の分かり易いイラスト、グラフ、概念図、といった図表を交えて図解で分かり易く解説するという構成になっています。
また各章の終わりには、『コラム』欄が設けられ、『モノづくりは、人づくり』といったトピックスが取り上げられコメントされています。
それでは、章を追って概要を紹介します。
第1章では、「見える化の意義」
と題して、製造現場の見える化について以下の7つの観点から見えないことの罪悪を取り上げそれがどのような「ムリ・ムラ・ムダ」などの弊害を生むかを説き、裏返しで見える化の意義・メリットを考察するというスタイルで見える化を解説しています。
- モノ
- 4M(人、施設・設備、方法、原材料)
- QCDS(品質、コスト、納期、安全性)
- 情報
- 日常管理
- 方向性および思い
- 全体および経営
さらに見える化のねらい(ムダの徹底排除、人づくり、見える化のねらい)、見える化の役割(5S+見える化+人づくり)について確認しています。
以降の章で上記の7つの視点から見える化の手法を説くという展開になっています。
第2章では、「モノを見える化する」
と題して、モノ(材料・製品・仕掛品・加工品・不良品・工具・治具・ゲージなど)が見えない状態となると探索・手待ち・つくり過ぎ、不良などのムダが発生するが、その要因の一つが5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)の不徹底にあるとして、5Sの徹底によるモノの見える化のための手順を解説しています。
整理のポイントは思い切ってすてることとした上で、5Sカード/赤札での見える化/5S改善シートでの見える化/不要品棚ざらし・迷い箱での見える化/整理基準での見える化について具体的な事例を交えて解説しています。
また整頓のポイントを解説した上で、定置・定品・定量(3定)での見える化/ロケーションの見える化/形跡整頓などでの見える化について解説しています。
また清掃の推進について解説し、清掃当番表での見える化/道具の見える化について解説しています。
そして、清潔の推進のポイントを解説した上で、色彩基準での見える化/5Sの定着化の見える化について解説しています。
さらに躾の推進のポイントを解説し「正しい状態の見える化」について解説しています。
第3章では、「4Mを見える化する」
と題して、生産に必要な要因系(インプット)の項目の4M(Man:人、Machine:施設・設備、Method:方法、Material:原材料)が見えないとムリ・ムダ・ムラが生じるとし、ムリ・ムダ・ムラを排除する観点から4Mの見える化について解説しています。
人については、動きと働きの見える化/人と機械の動きの組合せの見える化/人の動きと機械配置の見える化/ 一人工の仕事の見える化/大部屋化での見える化/人員とスキルの見える化/動線・作業範囲の見える化/バラツキ・繁閑の見える化についてのアプローチを解説しています。
施設・設備については、設備操作の見える化/レイアウト・設備の見える化/設備状況の見える化/設備保全の見える化/工程能力の見える化の方法を解説しています。
方法については、標準作業の見える化/仕事を作業者任せにしないための見える化/作業手順書・作業要領書での見える化/段取り替えの見える化を取り上げて解説しています。
原材料については、ワーク・部材の見える化/在庫量・発注点の見える化のための方法について解説しています。
第4章では、「QCDSを見える化する」
と題して、製品における結果系(output)の事項になるQCDS(Q:Quality(品質)、C:Cost(コスト)、D:Delivery(納期)、S:Safety(安全))を見える化し、これらに関わる損害を未然防止する方法について解説しています。
品質については、不良品の見える化/ニンベンのついた自働化での見える化/不良原因の因子の見える化/品質保証の見える化についてのアプローチについて解説しています。
コストについては、原価の見える化/工数の見える化の手法について解説しています。
また納期について、物流の見える化/引き取り・運搬の見える化/出荷・荷受の見える化について解説しています。
さらに安全については、労災予防の見える化/安全第一の見える化/機械類の安全性の見える化/健康状態の見える化を取り上げ解説しています。
第5章では、「情報を見える化する」
と題して、情報が見えないと以下の7つのムダが発生するとして、情報の見える化によって7つのムダを排除する方法について解説しています。
- つくり過ぎのムダ
- 手持ちのムダ
- 運搬のムダ
- 加工そのもののムダ
- 在庫のムダ
- 動作のムダ
- 不良をつくるムダ
ここでは、今日の仕事の見える化/進捗・出来高の見える化/図面・仕様書など紙媒体情報の見える化/電子媒体情報の見える化/情報の流れの見える化といったテーマを取り上げ解説しています。
第6章では、「日常管理を見える化する」
と題して、製造現場で求められる生産管理・購買管理・在庫管理・工程管理・品質管理・設備管理・原価管理・安全管理・労務管理などの日常管理についての見える化のための方法を解説しています。
日常管理の見える化については、職場のルールの見せる化/異常の見える化/“表準”の見える化・標準化/改善ストーリーの見える化/ PDCAの見える化/在庫水準を下げれば、問題が見える/各種日常管理項目の管理板での見える化/変化点管理板による変化点管理の見える化といったテーマを取り上げ解説しています。
第7章では、「方向性および思いを見える化する」
と題して、お互いに何を考えているのか、何をしたいのか、何を助け合えるのか、といった組織の思いが見え、進むべき方向性が一致したときにはじめて人が経営資源としてシナジー効果を発揮することができるとして、方向性および思いを見える化する方法を解説しています。
そのためにあるべき姿・ありたい姿の見える化/目的・方針・目標の見える化/活動の見える化/気づきの見える化/知恵の見える化/見える化のレベルアップといった見える化のポイントを解説しています。
第8章では、「全体および経営を見える化する」
と題して、部分最適でなく工場全体、会社全体のための全体最適を図る観点からの見える化の手法について解説しています。
全体と経営の見える化に関して、工程の概要の見える化/工場全体の鳥瞰/モノと情報の流れ図を描く工場全体の見える化/改善成果と経営の見える化/在庫運転資金の見える化などを取り上げて解説し、見える化で人を動かすことができて会社は変わると説いています。
<<本書で何が学べるか?>>
本書では、製造現場における見える化の意義と効果の確認にはじまり、見えないことで何を失っているのか、創意あふれるモノづくりの現場とはといった事柄について、モノ、4M(人、施設・設備、方法、原材料)、QCDS(品質、コスト、納期、安全性)、情報、日常管理、方向性および思い、全体および経営の観点から「見える化」の実例とその克服方法について豊富な図版とやさしい解説で紹介しています。
<<まとめ>>
自社のカイゼンのためのヒントを得たい人は、本書を読んでみて下さい。
なお本書の目次は、以下の内容です。
第1章 見える化の意義
第2章 モノを見える化する
第3章 4Mを見える化する
第4章 QCDSを見える化する
第5章 情報を見える化する
第6章 日常管理を見える化する
第7章 方向性および思いを見える化する
第8章 全体および経営を見える化する
特別編 見える化度が企業のレベルを表す
見える化診断100
<<見える化関連の書籍のリンク集>>
(広告)
- 2009年11月04日
- 見える化、改善、ムダ取り、ポカヨケ
- コメント(0)